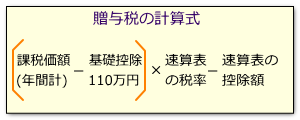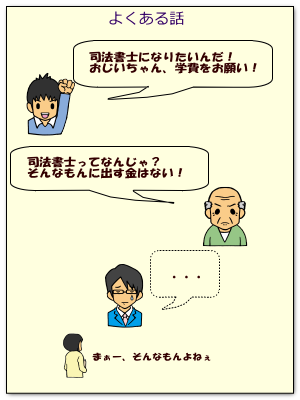新築やリフォームによる優遇税制
住宅の購入や新築、増改築やリフォームなどをした場合には、一定の条件を満たすことによって、所得税や住民税・固定資産税等について優遇を受けることができます。
ローンを利用せずに自己資金のみで住宅を取得する場合、住宅ローン控除は利用できません。
住宅ローン控除が利用できない代わりに、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を自己資金のみで新築・取得した場合に所得税が控除される制度として『投資型減税』制度があります。
住宅ローン控除と同じく、平成26年4月1日から消費税が8%に引き上げられることにともない、制度が拡充されています。
投資型減税とは
正式名称は「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」といいます。

認定長期優良住宅(消費税8%増税後は認定低炭素住宅も対象)を現金で取得した場合、確定申告によって一定の所得税が控除されるというものです。
所得税の控除額が、年間で納めた所得税を超えることはありませんが、控除しきれなかった場合は翌年の所得税から控除を受けることができます(翌年も確定申告が必要)。住宅ローン控除と異なり、住民税からの控除はありません。
なお、投資型減税と住宅ローン控除を、同じ人が同時に併用することはできません。
しかし、共有者の一人が住宅ローン減税を受け、別の一人が投資型減税を利用するということは可能です。たとえば、住宅ローンを借りたご主人が住宅ローン控除の適用を受け、自己資金を出した奥様が投資型減税を利用することができます。
また、投資型減税は、1棟の建物を複数の方で共有している場合には、要件を満たした共有者すべてが受けることができます。
投資型減税の内容(平成26年4月1日~平成29年12月31日)
投資型減税も、平成26年4月からの消費税率引上げにあわせて大幅に拡充されました。

(注1)入居時期がH26.4.1以降であっても、住宅に係る消費税の税率が5%の場合には、改正前(H26.3.31以前)の制度が適用されます。
(参考:旧制度)
対象住宅:認定長期優良住宅のみ(旧制度では低炭素住宅を含まない)
最大控除額:50万円
掛かり増し費用は構造によって異なる
鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造:36,300円/㎡
木造・鉄骨造その他:33,000円/㎡
(注2)その年の合計所得金額が3,000万円を超える方は、控除を受けることはできません。
投資型減税を受けるための要件
住宅の新築または取得で、投資型減税の適用を受けるための主な要件は、次の通りです。
(1).「認定(長期優良・低炭素)住宅の新築」又は「建築後使用されたことのない認定(長期優良・低炭素)住宅の取得」であること。
(2).新築または取得後6ヶ月以内に居住すること
投資型減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。 また、住宅の引き渡し、または工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があります。居住しているかどうかは、住民票により確認されます。
もちろん、別荘・セカンドハウスや賃貸用の住宅は、対象となりません。主として居住する1つの住宅に限ります。
(3).控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
(4).登記簿上の家屋(マンションなら専有部分)の面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
・対象となる住宅の床面積が50㎡以上であることが要件となっています。この床面積の測定方法は、不動産登記上の床面積と同じです(戸建住宅の場合は壁心、共同住宅の場合は内法により測定)。
・店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
(5).居住した年とその前後2年間の計5年間、次の制度の適用を受けていないこと
A 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
B 居住用財産の譲渡所得の特別控除
※「特定の居住用財産の買換えの特例」を利用した課税の繰り延べは、重複して適用を受けられます。
申請方法
投資型減税の適用を受けるには、入居した年の収入についての申告を行う際(つまり翌年の確定申告時)に、税務署に必要書類を提出します。
【主な必要書類(詳細は税務署にご確認ください)】
・確定申告書A
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
・住民票の写し
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し)
・住宅用家屋証明書(写し可)、又は認定長期優良住宅建築証明書(認定低炭素住宅建築証明書)
・家屋の登記事項証明書
・工事請負契約書の写しや売買契約書の写し
・源泉徴収票(給与所得者)
※控除し切れなかった額を翌年の所得税額から控除する場合には、再度確定申告が必要です。
その場合に提出するのは、少なくとも次の通りです。
・確定申告書A
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
・源泉徴収票(給与所得者)
厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂
厂厂厂厂
厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷
厂厂 お問い合わせはこちら
厂 無断転載禁止